昭和の片隅で──私の原風景と、子どもの私が見た世界
押し入れの中で、ひとり、じっと息をひそめていた幼い私。
真っ暗な闇の中で聞こえてくるのは、母の怒鳴り声──
それも、ヒステリックな叫びに近い声でした。
それが、私の記憶の原風景です。
まな板の音、絵本を読む声──それは知らない誰かの家庭

まな板の「トントントン」という音。
湯気の立ちのぼる夕げ。
やさしい声で絵本を読む母親──
そんな、どこかの家庭の風景。
昭和のドラマでよく見かける、温かい団らんのひととき。
けれど私の幼少期には、そうした光景は一度もありませんでした。
店をたたんだ父

両親は、結婚当初、田舎町の小さな商店街でお店を開いていました。
でも商売はなかなか軌道に乗らず、資金もほとんどないまま見切り発車だったようです。
その日暮らしの自転車操業。
売上でなんとか食いつなぎ、やがて仕入れすらできなくなって、父は店を離れ、サラリーマンになりました。
「そんな儲からない店、早くやめちゃえばいいのに」
大人になった今ならそう言いたくもなりますが、当時の私はただの子ども。
そんな事情があるなんて、知る由もありませんでした。
居留守という名の隠れんぼ

記憶の中で、今もはっきり残っている場面があります。
「ここに隠れてて! 出てきちゃだめ!!絶対に声を出しちゃダメよ!!!」
母が血相を変えて、階段の奥に私を押しやることが何度もありました。
後になって知ったのですが、仕入れ先への支払いが滞り、訪問を避けるための居留守だったのです。
私は階段の隅で、じっと息を殺していました。
家計はいつも火の車──それでも、当時の私は「貧しさを我慢していた」という実感は、あまりありません。
靴屋のおじちゃんと、忘れられない匂い

母に遊んでもらった記憶は、ほとんどありません。
遊び場は学校の裏山や、近所の商店街。
商店街の店先をのぞき込んで、大人たちが忙しそうに働く様子を見るのが好きでした。
特に、三軒隣の靴屋さんは居心地がよくて──
おじちゃんが靴を直す手元を、じっと見つめている時間がたまらなく楽しかった。
おじちゃんは私を叱ることもなく、にっこり笑ってくれました。
皮靴と接着剤のにおい、そしておじちゃんの汚れたエプロン──
それらは、今でも心の奥に残る懐かしい香りです。
「妹を寝かせてから遊びなさい」──小さな母親のように

外で遊ぶとき、母は必ず条件をつけてきました。
「妹を寝かしつけてから遊びに行くのよ」
私が遊びに出ると、妹がついて回り、母が手を焼くからという理由でした。
この条件をクリアしないと、外へ出ることは許されません。
妹はいつも、私の後を追いたがる子で──
母に代わり、歯医者の付き添いや保育園の送り迎えも、私の仕事でした。
妹が大きくなるにつれて、私は自然と彼女を連れて遊びに出るようになっていきました。

姉妹というのは不思議なもので、面倒を見なさいと言われる前から、どこか放っておけない存在になっていたのです。
それでも私は、いつも母の顔色をうかがっていました。
「機嫌が悪くなりませんように」
「怒らせるようなことをしませんように」
そんな小さな祈りを心の中に持ち続けながら、毎日を過ごしていた気がします。
お店を閉めた日──さよなら、靴屋のおじちゃん

そんな暮らしが、私が8歳になる頃まで続きました。
そしてある日、両親はお店をたたむことを決断したのです。
開店からわずか9年──
店を閉めて、親戚を頼りに、別の町へ引っ越すことになりました。
近所には、大好きなお友だちがたくさんいました。
だからこそ、お店をたたむことよりも、慣れ親しんだ商店街を離れることの方が、ずっとつらかったのを覚えています。
通い慣れた銭湯、いつもニコニコしていた太っちょの八百屋のお姉さん、ちょっと怖かった布団屋のおじさん…
そして何より、靴屋のおじちゃんとのお別れが、とても悲しくてたまりませんでした。
あのころ、白髪まじりの頭に少しハゲかかったおじちゃん──
きっともう、この世にはいないのだろうなと思います。
叶うことなら、もう一度だけ、あのおじちゃんに会いたい。
子ども心に感じたやさしさは、今も胸の中に生き続けています。
はじめてのアパート暮らしに、少しときめいた

新しい引っ越し先は、父の会社の社宅アパートでした。
初めてのアパート暮らしは、幼い私にも、それはちょっぴり都会的に感じられたのです。
白い壁、ドアノブ、玄関の扉──
見慣れた木戸ではないものに囲まれて、どこを見ても新鮮な光景ばかり。
引っ越したばかりの頃の寂しさも、いつしか消えていきました。

社宅には、一つ年上のお兄ちゃんが住んでいて、よく近所の公園に誘ってくれました。
当時小学3年生だった私は、まだ自転車の補助輪が取れておらず……
ちょっと恥ずかしくもありました。
「大丈夫!怖くないよ。僕が後ろ持ってあげるから」
お兄ちゃんは、そう言って何度も練習に付き合ってくれました。
そのやさしさに支えられて、引っ越し先での暮らしは、ぐんと楽しいものへと変わっていったのです。
「あのお兄ちゃん、今ごろどうしているかな……元気でいてくれるといいな」
ふとしたときに思い出す、懐かしくもあたたかい記憶です。
裁縫で支えた母の背中

新しい社宅での生活が始まってから、母は裁縫の腕を活かし、ミシンを使った内職に精を出すようになりました。
ミシンの音と夜なべ仕事
ミシンの仕事がない時には、ボタン付けや細かい縫い物も引き受けて──
母は、文句ひとつ言わず、黙々と働いていました。
けれども、内職の仕事はとても忙しいわりに、報酬は決して良いとは言えなかったようです。
それでも、父は母が外に働きに出ることを望みませんでした。
お金の価値や、効率の良い働き方など、子どもの私にはまったくわからなかったけれど……
今になって思い返すと、夜遅くまでミシンの音がしていたのを、ふと思い出します。
枕元のサプライズ──二匹のクロネコ

ある朝、目を覚ますと、枕元に二匹のクロネコのぬいぐるみが並んでいました。
母が、私と妹のために夜なべ仕事で作ってくれたのです。
きっと疲れていたはずなのに──
寝る間も惜しんで、そっとプレゼントしてくれた、母からの贈り物でした。
その二匹のクロネコのことは、長い間忘れていたけれど、
こうして振り返ってみると、じんわりと心にしみるような、うれしい思い出になっています。
母からの贈り物に込められた想い
母の当時の想いが、ほんの少しだけわかった気がするんです。
子どもたちをかまってあげられない辛さや、生活の苦しさ、寂しさ──
そんなさまざまな思いを胸に、それでも一生懸命、クロネコに愛情をこめてくれたのでしょう。
そんな母の姿は、しばらく変わることなく続いていきました。
母に代わって過ごす、放課後の時間
学校から帰ると、ランドセルを放り出すようにして母の代わりに買い物に出かけ、妹の世話をする──そんな日々が、当たり前になっていました。
台所に立ち、夕食の支度を手伝ったことを、今でも思い出します。
読書感想文と、買ってもらえなかった本
夏休みの宿題といえば読書感想文。
でも学校から配られる「推薦図書」は、買ってもらうことができませんでした。
本が欲しいとせがんでも、母は静かに首を振るだけでした。
たった一本の鉛筆が、買ってもらえなかった
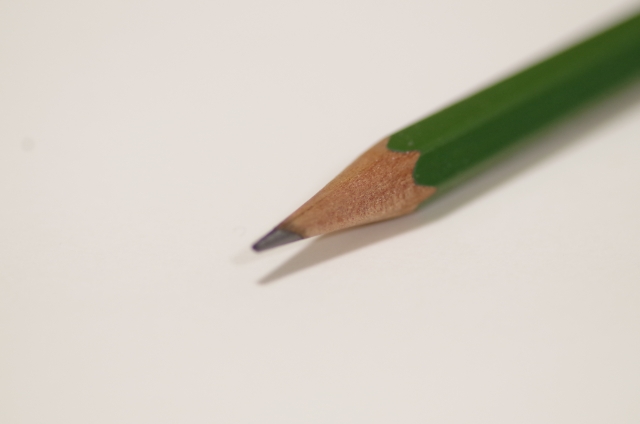
「恵まれない子供たちに愛の杖」という名の鉛筆
ある時期になると、学校でチャリティーのために鉛筆の販売がありました。
確か「恵まれない子供たちに愛の杖」と名前がついていたと思います。
子どもながらに「たとえ一本でも買って、寄付したい」と願いました。
それでも、鉛筆は買ってもらえなかった
けれど、その一本の鉛筆さえ買ってもらえませんでした。
今思えば、他人に寄付する余裕なんて、我が家にはなかったのです。
「お母さんのケチ!」
口をとがらせて言い放った私に、母は何も言い返しませんでした。
家計の苦しさを、本当には理解していなかった私は、そのときの母を決して「いい人」だとは思えませんでした。
運動会と参観会だけは、来てくれた母

母は相変わらず、忙しく働いていました。
それでも、運動会と参観会だけは欠かさず来てくれました。
参観会では、決まっていねむり
授業参観のあとの懇談会では、決まっていねむりをしていました。
疲れていたのでしょう。
少し恥ずかしい気持ちと、それでも母がそこにいてくれるだけで、心のどこかが落ち着いていたのを覚えています。
ポプラ並木の陰で、そっと応援してくれた

運動会のとき、ポプラ並木の陰から、そっと応援してくれていた母の姿は、今でも鮮明に思い出せます。
派手な応援はなかったけれど、あの静かなまなざしが、すべてを語っていた気がします。
それでも、母との思い出は少なかった
そんな小さな出来事が、母との数少ない思い出です。
あとは、毎日働いていた母の背中と、夕食の支度をする私自身の姿ばかりが思い出されます。
「お姉ちゃんだからしっかりしなさい」

母は何かにつけて、私にこう言いました。
「お姉ちゃんなんだからしっかりしなさい!」
「お姉ちゃんは、常に妹たちの見本にならなきゃいけないの!」
長女としての責任と、募る不公平感
三人姉妹の長女だった私は、妹たちよりも厳しく叱られました。
まだ子どもだった私は、次第に不公平を感じるようになり、母の言葉が重荷になっていきました。
わだかまりとして残った、母への思い
母への愛情は、いつしか深いわだかまりへと変わっていきました。
それは、幼い私の未熟さでもあり、母の苦しみを受け止めきれなかった心の未完成でもありました。
おとなになって気づくのは、
私は「母の機嫌を損ねない子ども」であろうとしていたということ。
「よい子でいなきゃ」
「手をかけさせないようにしなきゃ」
そんな思いが、当たり前のように自分の中に根を張っていたのです。

いつの頃からか、感情を外に出すのが怖くなりました。
うれしいことも、悲しいことも、「伝えてはいけない」と自分に言い聞かせる癖がついていたのです。
それはまるで、押し入れの中で膝を抱えていた、あの頃の私のまま。
「静かにしていなきゃ」「ここから出ちゃいけない」
そんな風に、自分自身を閉じ込めてしまうようになっていました。
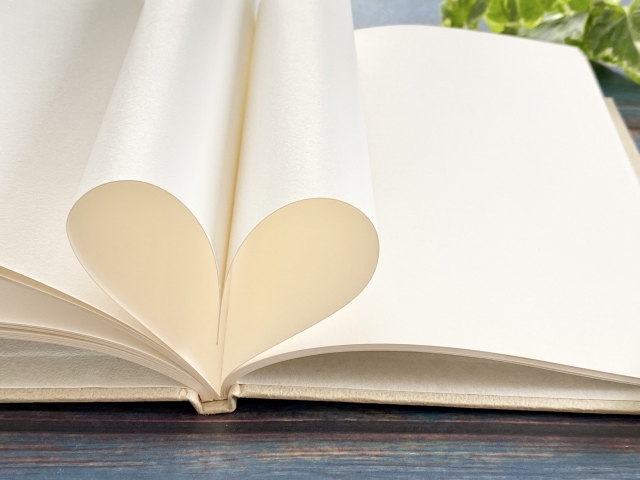
けれども、今になって思います。
あの頃の私に、そっと声をかけてあげたい。
「もう出てきていいんだよ」
「あなたの気持ちを、ちゃんと聞いてくれる人が、きっとどこかにいるよ」って。
靴屋のおじちゃんの静かな笑顔や、裏山の木々のざわめき、
そんな小さな温もりが、私の中の子どもをそっと慰めてくれていたように思います。
そして、あの記憶たちは、今の私の根っこになっている。
だからこそ、今、こうして「ばぁばちゃんの台所カフェ」という場所で、
誰かの心に、小さな灯りをともすような文章を書いているのかもしれません。
お読みいただきありがとうございます。
心の中のお店を、ばぁばちゃんは少しづつ開けていこうと思います。


